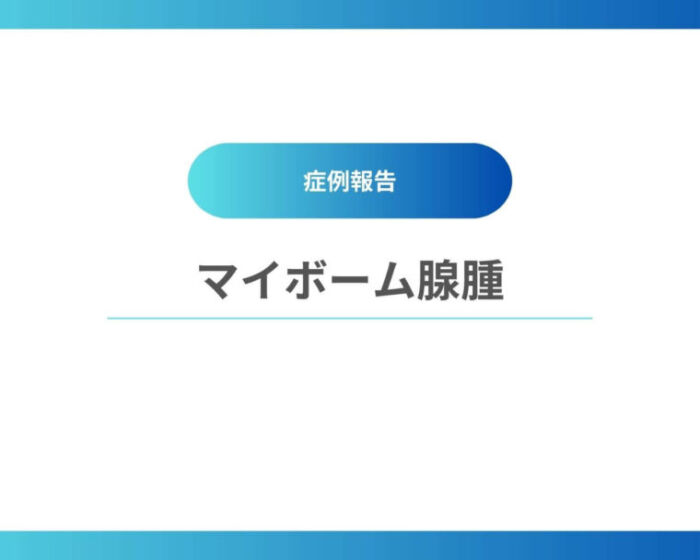今月も名古屋で開催された「手術屋・中島先生」のHJSセミナーに参加してきました。
今回のテーマは「頭頚部外科の総論」です。
もくじ
Toggle頭頚部外科とは
頭頚部外科とは、その名の通り「首より上」の領域を扱う外科です。
この部位は、感覚・運動・嚥下・発声・呼吸・審美といった多重の機能が密接に関わっており、さらに神経・血管・筋群が複雑に入り組んでいます。
そのため、腫瘍や疾患の制御、外傷の整復を行う際には、機能障害を最小限に抑えながら正確に手術を行うための高度な解剖学的理解と手術計画が欠かせません。
つまり頭頚部外科は、「疾患を治す」だけでなく、生きる質(QOL:Quality of Life)の維持が求められる分野なのです。
嚥下・発声・表情・審美・社会復帰といった要素を踏まえ、単なる切除ではなく、機能温存・再建・リハビリを含めた包括的な外科が必要になります。
頭頚部外科の難しさ
例えば口腔内に発生する悪性腫瘍(線維肉腫、扁平上皮癌)では、転移性は低い一方で局所浸潤性が高いものが多く、確実に広範囲を摘出できるかどうかが治療の鍵となります。また初期の悪性黒色腫(メラノーマ)でも広範囲摘出により完治できる可能性があります。
そのため、下あごの小さな腫瘍であっても、時に下顎全域を摘出しなければならないケースがあります。
しかし、顎を失うということは、**食べるという「生きるための基本的な機能」**に大きな影響を及ぼします。
必要以上に温存すれば再発のリスクが高まり、広く切除すれば機能が損なわれる――まさに難しい選択が求められる分野です。
再建外科とQOL
そこで重要になるのが、「機能を持たせた再建手術」です。
たとえば舌の動きを可能な限り残すよう工夫すれば、たとえ顎を失っても、舌を使って食事ができるようになることがあります。
このように、腫瘍制御と機能再建の両立が実現できれば、患者はQOLを保ちながら生きていけるようになります。
そのためには、緻密な頭頚部の解剖知識と、機能を損なわない縫合や再建の技術が必須です。
中途半端な手術では患者を助けられない。
本当に「完治」を目指すなら、積極的な切除と機能再建の両立こそが求められます。
今回の学び
頭頚部外科は、多くの獣医師にとってハードルの高い分野だと思います。
知識・経験・手技の複雑さ、さらには術後管理の煩雑さもあり、どうしても踏み込みにくい領域です。
しかし、それを補うための教科書や資料も限られており、だからこそこのようなセミナーで学ぶ機会は非常に貴重です。
今回学んだことは、決して今日明日で身につくものではありません。
一歩ずつ、日々の勉強と鍛錬を積み重ねることの大切さを改めて感じました。
余談:医学の変化と「QOL」という視点
セミナーの中で印象的だった小話があります。
最近の医学論文では、「有意差」という言葉を使う論文が減ってきているという話でした。
これは、「切った・切らない」で生存期間を比べる時代ではなく、患者がどう生きたか・どう過ごせたかという「質」が重視される時代に変わってきているということです。
獣医療においても、動物の生活の質だけでなく、**飼い主さまの生活の質(QOL)**をどう支えるかが、これからますます重要になると感じました。
まとめ
今回のセミナーを通して、頭頚部外科の奥深さと、その背後にある「生きる質を守る外科」という考え方に強く感銘を受けました。
これからも、より多くの患者を救うため、日々学び続けていきたいと思います。
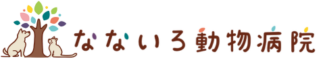
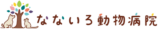


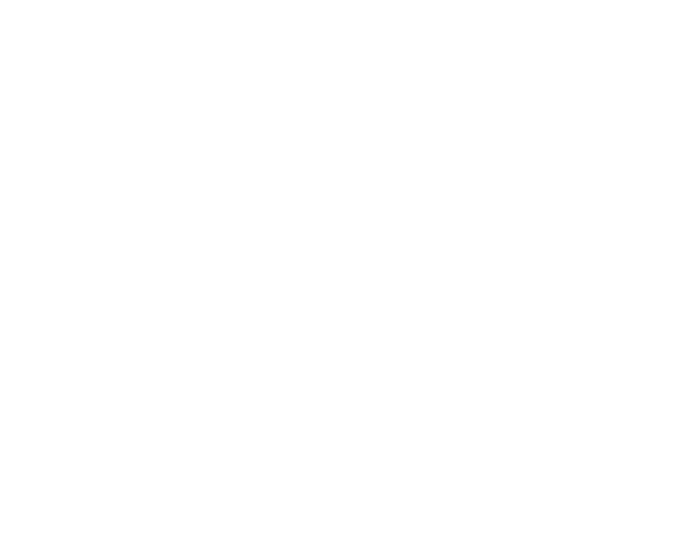
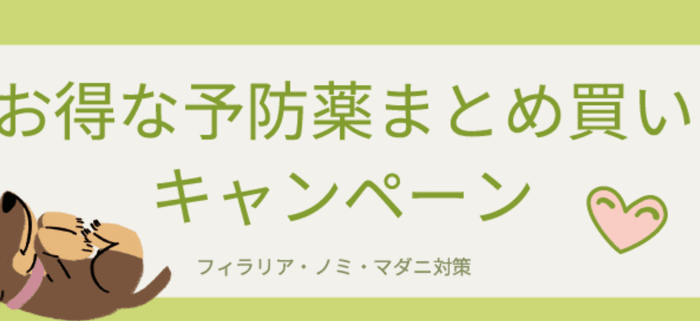
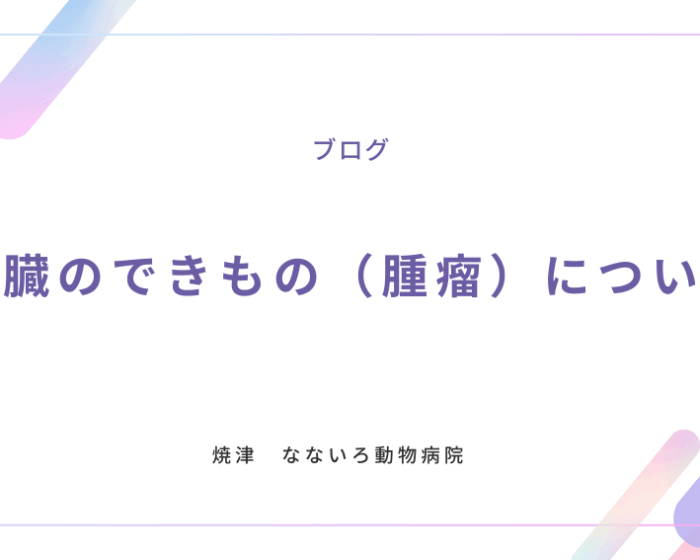
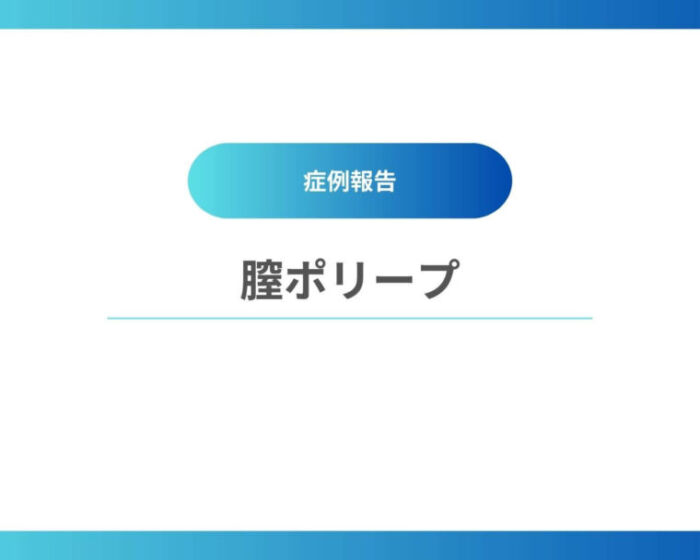
![[定休日]月曜日/月曜日が祝日の場合、翌日振替休業1 (1)](https://nanairoah.com/wp-content/uploads/2025/12/[定休日]月曜日/月曜日が祝日の場合、翌日振替休業1-1-thegem-product-justified-landscape-xl.png)